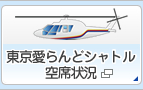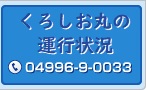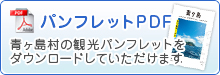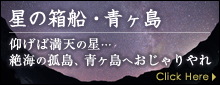特産品
野菜やお芋、魚や貝たち
移り変わる季節を感じ、山や海で採れる野菜やお芋、魚や貝たちは日々変化していきます。青ヶ島での生活は、これらの旬を敏感に感じます。
農作物
・島唐辛子(6月~12月)

本土から持ち込んだ種を青ヶ島で植えると、辛みが増し、青ヶ島で育った唐辛子の種を本土で植えると辛みが減る・・青ヶ島の気候風土が、唐辛子を辛くするようです。刺身のしょう油皿には、島唐辛子が1つ。箸で少しだけ潰して辛みを加え、いただきます。島だれなどにも島産の唐辛子を使い、青ヶ島の農作物で欠かせないものになっています。
・島きゅうり(6月~9月)

一般的なきゅうりよりも太くて大きい。大きいものは、長さ20センチ、幅5センチにもなります。若く緑色のものは塩でもんで、〝きゅうりもみ〟などに。時間が経ちあざやかな黄色になったものは皮をむき、種を取って炒めものなどにします。緑色の島きゅうり、黄色の島きゅうり、好みは人それぞれです。
・かんも(11月)
〝かんも〟とは、サツマイモのこと。青ヶ島の焼酎造りにはかかせない作物です。紅あずま、マツミかんも、せいきかんも、にんじんかんも、紫かんもなど、いろいろな種類のかんもを育てています。かんもを干して作った乾燥芋〝キンボシ〟などの郷土料理があります。干したかんもを粉にし、団子にしたものは〝キンボ〟。かんも畑で、新芽の時期のみ採れる〝イモヅル〟とは、まさしくお芋のツルのこと。炒めものなどにします。

かんも

マツミかんも

せいきかんも

にんじんかんも
・里芋(11月)

青ヶ島の影の特産品、ホックリと粘り気の強い里イモ。ワセやナンキン、アカメなど、里芋にもたくさんの種類があります。里イモに〝しゅうで〟と呼ばれる魚の塩辛をつけて食べるのが一般的です。
青ヶ島で自生している食植物
・タラの芽(2月)

全国で見られる山菜。青ヶ島にも自生しています。天ぷらなどに。
・ててんこう(2月)
椿の木にできたばかりの実。白くて味はあまりしませんが、昔はおやつとしておいしくいただきました。現在はほとんど食べません。
・ノビル(青葉は3月~5月。球根は年中)
日本全土で見られるノビル。軟らかいうちは青葉を食べ、お目当ては地下にできた白い球根。ラッキョウのような形をしています。
・ツワブキ(2月~4月)

2月から4月にかけて、茎にフワフワした産毛が生えている新芽は食用としていただきます。香りがよく、岩海苔と一緒に煮物などにします。冬、ツワブキの花が青ヶ島中を黄色く色付かせます。
・イタドリ(4月初旬~中旬)

青ヶ島では〝イタドリ〟。茎を折るとポコッと音が鳴り、食べると酸味があることから〝スカンポ〟などと日本各地いろいろな名前を持ちます。和え物やいただきます。
・ヌクタチ(5月~6月)

〝ツルソバ〟のこと。伊豆諸島や紀伊半島以南に分布しています。味はすっぱく、新芽を和え物や天ぷらにします。
・ノダケ(4月後半~5月末)

青ヶ島の筍はノダケとニガダケがあります。両方とも笹のような太さ。香ばしく網で焼きあげ、皮をむいて食したり、煮物などにします。
・ニガダケ(6月中旬~7月中旬)

ノダケの時期がすぎるとニガダケの季節、梅雨とともにニガダケのシーズンがやってきます。名前の通り苦味のあるニガダケ。煮物などに。
・自然薯(11月)
秋になり地上部が枯れる頃が収穫時期。地中に深く伸びる自然薯を掘り起こします。自然薯の実〝ムカゴ〟は、〝カンゴ〟と呼ばれ、カンゴごはんなどに。
・エベズ(9月~10月)
最初は青く、熟れると紫になる小さな山ブドウです。青いうちは酸味が強く、漁師はエベズを片手に海へ。釣れた魚カワハギなどに、酸味としてエベズをふりかけいただきます。
・カブツ(11月末~1月)
青ヶ島でいう〝カブツ〟とは〝だいだい〟のこと。大変貴重な果物です。焼酎に入れたり、鍋のつゆに入れたり、三杯酢で味付けしたお魚にふったりと大活躍。取らないでいると、腐ったり落ちたりせず、そのままの状態で残ります。水分は減っていきますが、来年になるとまたみずみずしい果物になります。青ヶ島に昔から自生しており、昔からあるものは表面がゴツゴツ。見かけは悪いですが、味は最高です。
・明日葉(年中)
「今日摘んでも明日には新しい芽を出す」という明日葉。とても生命力の強い植物です。伊豆諸島などで自生する日本固有の健康野菜で、食物繊維やビタミン類など、現代人に欠かせない様々な栄養素が含まれています。青ヶ島を散策中、あちこちに明日葉を見つけることができ、島の家庭料理には欠かせない野菜です。ゆでてお浸しや、ワサビマヨネーズの和え物、椿油で炒めものなど。大きく硬くなった明日葉は、粉末にしてパンやお菓子などに。
魚や貝や海藻
・クジラヨ(年中)
クジラ?とよく間違えられますが、島で呼ばれる〝クジラヨ〟とは〝テンジクイサキ〟のこと。〝ヨ〟は島言葉で魚を意味します。島の魚となっており、青ヶ島の代表的な魚です。筒切りにして塩焼きにしたり、お刺身や酢漬けなどにしていただきます。プリプリとした皮が特徴的で、お刺身も皮付きでいただきます。
・岩海苔(12月~2月)
海水が冷たく、荒れた海に生える岩海苔。海が穏やかになった隙を見計らい、堤防や海岸沿いで採取。海苔めしや、海苔鍋などにします。
・ハンバ(12月~2月)
海苔の一種。幅が広いことから〝ハンバ〟と呼ばれています。ごはんと一緒に炊きあげて、ハンバめし。また、明日葉とハンバのかきあげに。
・シボウサキ(12月~2月)
クジラヨが好んで食べる赤紫色の海藻。お吸い物などにします。シボウサキの採れる12月から2月は、クジラヨもおいしくなります。
・ヒラミ(年中)
潮の引く5月ごろは収穫がしやすく、比較的大きなものが獲れることが。ヒラミごはんやヒラミの味噌汁。ヒラミの塩づけなど。
・セノカミ(年中)
亀の手に似ていることから呼ばれる〝カメノテ〟のこと。岩の間にしがみつくように生息する甲殻類です。味噌汁や、酒蒸しに。
・かんべぇめ(年中)
うつぼの一種で、細くて長い。炭の上で干したかんべぇめは煮物などに。生や冷凍したものはぶつ切りし、天ぷらなどにします。