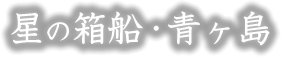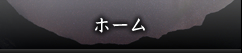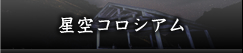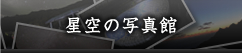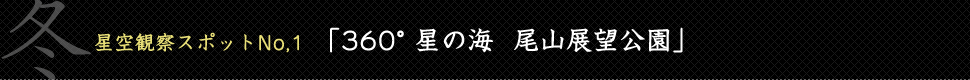「カノープス」という星を知っていますか…? 全天で1番明るく輝く"おおいぬ座"の恒星「シリウス」は有名ですね。そう、冬の王者・オリオンの左下に青白く輝くあの星です。「カノープス」とはその「シリウス」に次いで2番目に明るい"りゅうこつ座"の1等星で、ギリシャ神話に登場する船乗り(水先案内人)の名前に由来するという説があります。日本ではおおよそ北関東より南の地域で、条件の整った夜に限って、南天の水平線(地平線)ギリギリのところに姿を現す、とても珍しい星なのです。北緯36度弱の東京では、一番高く昇る時間帯でも地平線よりわずか約2度の高さにしかならず、"全天で2番目に明るいカノープス"であっても、実際には超低空なので夕陽のように光が弱まり赤っぽい色に見え、探すのが難しいのです。中国ではこのカノープスのことを「南極老人星」や「寿星」と名づけ、一目見ると長生きできて幸福になれるという伝説があります。
 「冬の星座たちとカノープス」 "カノープス南中(もっとも南の空高くになること)時刻"から約15分後に撮影。北緯32度半の青ヶ島からは水平線上これくらいの高さに見えます。肉眼では水平線と空の境目は真っ暗でわからないので思いのほか高く感じられ目立ちます。
「冬の星座たちとカノープス」 "カノープス南中(もっとも南の空高くになること)時刻"から約15分後に撮影。北緯32度半の青ヶ島からは水平線上これくらいの高さに見えます。肉眼では水平線と空の境目は真っ暗でわからないので思いのほか高く感じられ目立ちます。(撮影データ:16mm魚眼レンズ 絞りF2.8 露出66秒 ISO感度6400 小型赤道儀で自動追尾)
 尾山展望公園にある地球を形取った円形のモニュメントは、360°満天の星とマッチしています。この上に寝転んで星空を眺めるのも最高です。
尾山展望公園にある地球を形取った円形のモニュメントは、360°満天の星とマッチしています。この上に寝転んで星空を眺めるのも最高です。
標高約400メートルの"尾山展望公園"からは、ほぼ360度の水平線が見渡せ、晴れてさえいれば凍てつく冬の夜空一面に「星の海」が広がります。標高が高いので空気中のチリや水蒸気も少なく、とくに冬場は透明度がさらにUPするため、淡く見づらいとされる冬の天の川でもダイナミックに流れ実に神秘的な眺めなのです! それはもう宇宙船(名づけて「星の箱船・青ヶ島号」!)にでも乗って星空を見ているかのような錯覚に陥ります。"世界広し"といえどもこんな感覚を味わえるのは絶海の小さな孤島、ここ青ヶ島だけといっても過言ではないかもしれません。
南天の低空に姿を現すカノープスですが、青ヶ島の尾山展望公園は絶好の観察スポットとなります。まずなんといっても南の水平線まで見える視界の良さと街灯りが皆無で星の観察に最適な場所であることはもちろん、伊豆諸島最南端の青ヶ島は、北緯32度半、都心より約360km、緯度にして約3度、南に位置するので、カノープスは思いのほか高い位置に明るく輝いて見えるのです(つまり都心より約3°高く見える)。南の水平線付近まで晴れていることが条件なのですが、多少雲があっても根気よく待っていると雲間からギラッと力強く輝くカノープスに出会えるかもしれません。 わずかな時間しか顔を出してくれない、少々赤味がかったちょっと照れ屋な星ですが、青ヶ島ではこのカノープスのことを「ようこそ、いらっしゃい!幸福の星」という意味を込めて「おじゃれ星」と呼ぶことにしました!
カノープスが見えない時期であっても、もちろん青ヶ島イチオシの星空観察スポットであることは間違いありません。冬の天の川よりもずっと太く明るい夏の天の川や夏の風物詩「ペルセウス座流星群」など、ぜひ尾山展望公園から観察してほしいと思います。
 「カノープスの見つけ方」
「カノープスの見つけ方」冬の代表的な星座・オリオン座と全天一明るいシリウス(おおいぬ座)の下の方にカノープスはあります。
まずカノープスが見える時期ですが、10月下旬(明け方4時前後)〜4月上旬(日没後暗くなってからすぐ)くらいまでが観察好期です。12月・1月・2月、つまり冬が観察しやすい季節といえます。4月中旬〜10月中旬くらいまでは昼間で見えないのです。カノープスが見える時期でカノープスが一番高く昇る時間帯(南中といいます)は、冬の代表的な星座「オリオン座」と全天で1番明るい恒星・おおいぬ座の「シリウス」が空高く上がる時間とほぼ同じです。カノープスの見つけ方は、オリオンの有名な"三ツ星"の右下(オリオンの左足)の1等星「リゲル」と、おおいぬ座の「シリウス」から南の下の方へ辿っていけば見つけられます。オリオンの右肩(三ツ星の左上)の赤っぽい1等星「ベテルギウス」からリゲルとシリウスの間を通りまっすぐ南下させていってもわかりますし、オリオン座のベテルギウス、こいぬ座のプロキオン、おおいぬ座のシリウスで形作る「冬の大三角」を大きな"止まれ"の標識に見立てても探せます。
尾山展望公園からは、方角的には内輪山「丸山」〜池之沢の"地熱サウナ"の右側上空にかけてカノープスが見えることになります。ちなみに尾山から見ると地熱サウナ方向が真南です。